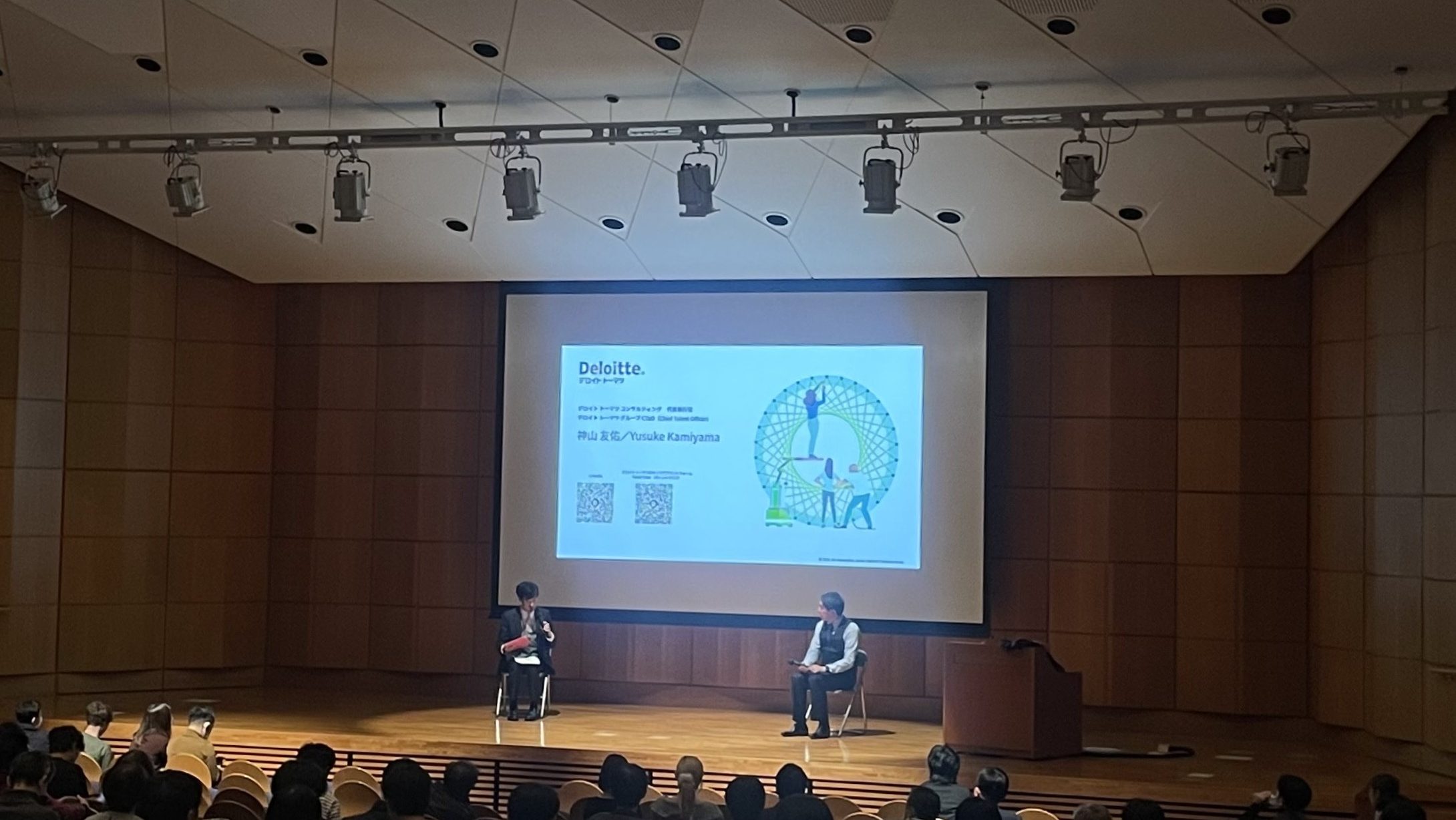外丸東眞選手 【写真=撮影】
慶大野球部で主将を務めた外丸東眞(環4)と、主軸として打線を牽引した常松広太郎(政4)。4年間の活動を終えた二人は、卒業後に全く異なる進路を選択した。外丸は社会人野球の強豪・東芝へ進み、プロ入りを目指す。一方、常松は外資系金融機関の内定を辞退し、米国シカゴ・カブス(マイナーリーグ)への挑戦を決断した。性格も進路も対照的な二人に、大学生活の振り返りと、それぞれの決断に至った経緯を聞いた。
外丸東眞、「準備」の 4年間とプロ入りへの道程
神宮球場のマウンドを守り抜くエースであり、150人を超える部員を束ねた主将、外丸東眞。2年秋の日本一という栄光と、思うような投球ができなかったラストイヤーの苦悩。引退を迎えた今、彼はその 4年間を「決して順風満帆ではなかった」と振り返る。社会人野球の強豪・東芝を経てプロを目指す彼に、その真実と展望を聞いた。
――「思い描いたものとは違った」苦悩と充実
取材の冒頭、外丸は率直に語った。「良いことも悪いこともあり、思い描いた形とは違いましたが、最終的にはやりきった」。外丸のキャリアを振り返ると、ハイライトは間違いなく 2年秋だ。リーグ戦優勝、そして明治神宮大会制覇。自身も「トップレベルのベストピッチング」と語る投球で優勝に貢献し、頂点の景色を知った。一方、上級生となり主将として迎えた最終学年は苦難の連続だった。「最後の一年間はあまり思い通りに投げられなかったので、4年生全体があまり上手くいかなかった」と責任を口にする。甲子園のマウンドも経験したが、大学のリーグ戦は質が違うという。高校が一発勝負のトーナメントであるのに対し、六大学は週末 2試合の連戦で、「負けても翌日には絶対に勝たなければならない」。敗戦を引きずれば、次の登板でまた崩れる。外丸は「今日はそういう日もある」と受け止め、翌日に向けて気持ちを切り替えることを徹底してきた。逃げ場のないマウンドで結果を求められ続ける経験が、投手としての精神を鍛えた。
――150人を束ねる重圧と、支えとなった絆
150人を超える組織の運営も困難を極めた。「人数が多いので、どうコミュニケーションを取るか、どうやって一つになっていくかという所は難しかったです」。部員全員のベクトルを合わせることは容易ではない。外丸は一人で抱え込まず、副将の今泉(商4)らとミーティングを重ね、「チームの結束」に注力した。特に意識したのは、接点の少ない下級生との対話だ。「下級生、特に1年生とは関わる機会が少ないので、積極的にコミュニケーションを取るようにしていました」。地道な積み重ねが、組織の末端まで血を通わせていった。そんな日々を支えたのが今泉だ。「副将として支えてくれ、毎週のように食事に行きました」。引退後には二人で台湾へ出かけ、束の間の休息を楽しんだ。また、寮生活では吉開(商3)が安らぎとなった。3年間同部屋で過ごし、練習後も生活を共にする存在は、主将として抱える緊張をふっと解く時間でもあった。
――雨の早慶戦でも崩れない「いつも通り」
外丸の真骨頂は、環境に左右されない「準備」にある。「心がけているのは『常にいつも通り』。法政戦であろうと早慶戦であろうと同じ気持ちで、同じ準備をする」。早慶戦は客席の熱が違い、試合前に気分が高まる瞬間はある。それでも「試合直前には集中力を高める」と語り、最終的には平常心へ戻していく。
象徴的だったのが大雨の早慶戦だ。心構え自体は変えない一方で、「あそこまでの雨はパフォーマンスに影響が出たと思う」と率直に認める。条件が厳しいほど「準備の価値」は増す。その信念が、外丸の投球を最後まで支えていた。規律ある生活もまた、準備の一部だった。朝6時起床、8時から練習。練習後は休息と食事、入浴、そしてストレッチに時間を割き、夜22時半には就寝する。外出は控え、食事にも気を配る。「自分勝手」「マイペース」と評されることもあるというが、それはすべての時間を野球に捧げるストイックさの裏返しでもある。オフの日は焼肉など食事が小さな息抜きで、遠出よりも温泉など近場で身体を休めるという。
――盟友・常松広太郎との対比
常松のパワーや打球速度、そして賢さを認め、外丸は強い信頼を置いていた。規律を重んじる外丸に対し、同期の常松は対照的だ。「(常松の能力をもらえるなら)テキトーなところ。僕は気にしすぎてしまうので、楽観的にいけるのは羨ましい」。ルーティンで不安を消す外丸と、状況に合わせて結果を出す常松。アプローチは正反対だが、互いにないものを持つからこそリスペクトし合える関係があった。
――社会人野球「東芝」、そしてプロへ
卒業後は東芝へ進み、視線は「2年後のプロ入り」にある。大学で磨いた制球力などに加え、これからは「球の強さやスピードなど、ボール単体で抑えられる『個の力』が必要」と冷静に分析する。現状に甘んじることなく、すでに次のステージを見据えているのだ。最後に、ファンへのメッセージを求めると、彼は感謝の言葉を繰り返した。「本当に多くの方が応援してくださっている、日本全国にいるなということを感じた 4年間でした」。神宮のマウンドで培った経験と揺るぎない準備力。外丸東眞は、新たなステージでもそのスタイルを貫き、静かに頂点を目指す。
常松広太郎、安定を捨てた「アメリカ挑戦」の真意と 4年間の軌跡
規格外のパワーで神宮を沸かせたスラッガー、常松広太郎。入学時は「ベンチ入りさえ想像していなかった」という男は、4年間でチームに欠かせない存在へと成長した。そして卒業後、彼は周囲を驚かせる決断を下す。世界的な金融機関・ゴールドマン・サックスの内定を辞退し、米・カブス(マイナーリーグ)への挑戦を選んだのだ。なぜ、約束された成功を捨ててまで険しい道を行くのか。その背景には、彼なりの合理的な判断と強烈な野心があった。

【写真=撮影】
――「7割は失敗」の中で掴んだチャンス
「野球は 7割ぐらい打てないんで、失敗ばっかりなんですけど」。そう語る常松だが、ここぞという場面での勝負強さは際立っていた。レギュラーを掴み取るきっかけとなったのは、3年春のキャンプ選考での出来事だ。結果を出さなければならない状況でデッドボールを受けた彼は、堀井監督に食い下がる。「デッドボールで終わるのがもったいなくて、『もう1打席ください』って言ったんです」。偶然巡ってきた再打席のチャンス。「俺のこと使えよ」とアピールして打席に入ると、見事にホームランを放った。その後も代打で結果を残し続け、レギュラー定着へとつなげた。「生意気なんですけど、チャンスをくれと言うのは別にマイナスにはならない」。リスクを恐れずに自己主張し、実力で回答を示す。その図太さが、彼の道を切り拓いた。
――カブス(マイナー)への挑戦理由
卒業後の進路について、常松は外資系金融機関か、野球かという大きな分岐点に立っていた。悩んだ末に選んだのはアメリカだった。その理由を、彼は「天井の高さ(アップサイド)」という言葉で説明する。「ゴールドマン・サックスから先のキャリアは、先人たちがいてある程度見えている。カブスに行って先が見えなくても、そっちの方が天井は高いと思った」。ビジネスは後からでも挑戦できるが、メジャー挑戦は今しかできない。
そうした思考を強固にしたのが、マイナー経験者でもある加藤貴昭部長の「野球をやりきった後のセカンドキャリアで活躍する人はアメリカにも沢山いる」という言葉だった。さらに、その決断を最後の一押しで支えたのは、親友であり新主将を務める後輩・今津(総 3)の存在だ。「今津家とも仲が良いんですけど、お父さんに話をしたら『お前がカブスに行かなかったら、もう縁を切る』と(笑)」。周囲からは無謀と言われるかもしれないが、「他人の声を気にして道を曲げるのは違う。自分が正しいと思った場所に矢印を向けて進むだけ」と言い切る。
――主砲・常松が欲した、エース外丸の「ミート力」
スラッガーの常松が外丸から「奪いたい」と語ったのは意外な能力だった。「僕はバッターなので、外丸の『ミート力』が欲しいっすね。普通に見ててすごい」。投手である外丸の打撃センスを、チームの主砲が絶賛する。規律を守り、繊細に準備を重ねる主将。本能に従い、豪快に道を切り拓く主砲。正反対のアプローチを持つ二人が、互いの個性を認め合い支え合ってきたからこそ、慶大野球部は神宮を熱く沸かせることができたのだろう。
――「眠い時に寝る」独自のスタイル
主将の外丸が徹底したルーティンを守るのに対し、常松の生活は自由そのものだ。「ルーティンは作らない」と言い、睡眠も「眠い時に寝る」スタンス。寮のベランダでチームメイトと朝まで語り明かすこともあった。「後から振り返った時に、そういう時間が大事だったなと思うので」。コンディションに神経質にならず、どんな状態でもありのままの自分で結果を出す。そのタフさが、異国の地での武器になる。
――支援への感謝と、塾生としての「義務」
見据える先は、野球の最高峰・メジャーリーグだ。「5年後、10年後にメジャーの舞台に立っていること」をベストとしつつ、アメリカでの経験はその後のキャリアにも活きると確信している。そして彼は、慶應義塾への思いを「義務」という言葉で語った。「最大限できるような活躍を自分のフィールドでして、後続の人たちも『この学校に入って良かった』と思えるような環境づくりをしっかりやっていくことは、義務だと思っています」。自らがアメリカで道を切り拓くことは、後に続く後輩たちが新たな選択肢を持てるようにするための開拓でもある。「自分がどんなフィールドに身を置くとしても、『もうこの学校じゃないとできなかった』と証明したい」。挑戦者と呼ばれながらも、その根底には深い「独立自尊」の精神が流れている。堅実に実力を積み上げ、日本球界の頂点を目指す外丸。リスクを恐れず、海の向こうで可能性に賭ける常松。神宮の杜で培った精神を胸に、それぞれの道で一回りも二回りも大きくなった二人が、再び笑い合う日が来ることを確信している。