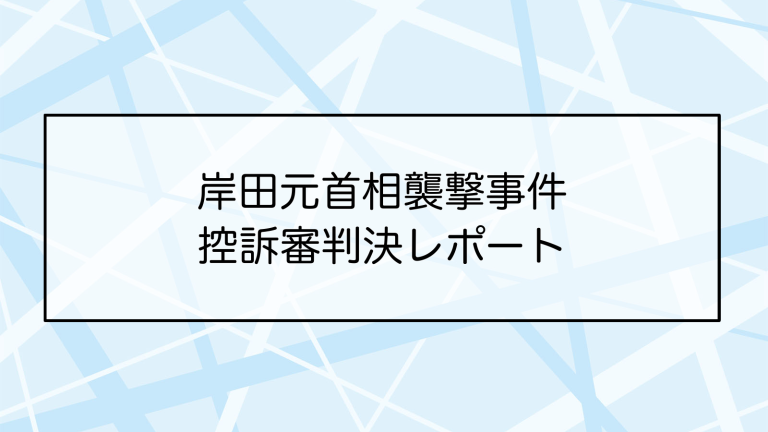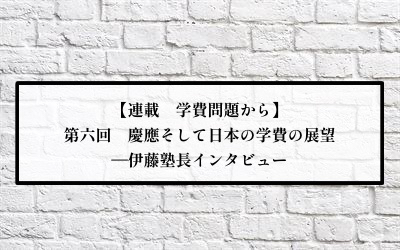片山杜秀教授【写真=提供】
昨年10⽉、当時の⽯破⾸相により「戦後80年にあたっての所感」が発表された。「なぜ戦争を防ぐことができなかったのか」という問いを正⾯から据えたこのメッセージは、今を⽣きる私たちに多くの教訓を投げかけている。⼀⽅で、その内容は必ずしも広く知られているとは⾔い難い。そこで本企画では、慶⼤法学部の⽚⼭杜秀教授に、所感の意義や背景を聞いた。
──今回戦後80年所感を読んだ率直な感想をお聞かせください。
第⼀印象としては、こんなに細かい話をするのかと。歴史の授業のようですね。拙著の『未完のファシズム』と似た視点もあるように思え、もしかして参考にしてもらったのかとも思いましたが(笑)。縦割りが細かく、統合的な意思決定のできない、近代日本の国家の仕組みの限界のような指摘についてですね。もちろん多くの学者が触れてきたことで、石破首相は北岡伸⼀先生に相談されたと公に報道されていました。私には何もなかったです(笑)。
──⾃⺠党内では戦後70年談話を上書きする必要はないという慎重論もあったなかで今回の80年談話が出された意義はどこにあるとお考えですか。
そのためには戦後70年のときの安倍談話を振り返らないといけないですね。70年で戦後にひとつケリをつける。80年、90年のときはもう首相談話は出さなくてよい。安倍談話にはそのような意図があったと理解しています。だから石破所感は要らないという意見も強かったのでしょう。
確かに安倍談話はたいへん巧妙な作品でした。保守向けとリベラル向けの文言がないまぜにされて、見事な玉虫色になっています。まず日本人の誇りを十分に喚起する。明治時代の評価については特にそうですね。「アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜き」とか、「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけ」たとか。保守的な人たちが喜ぶ。でも満州事変から第二次世界大戦までの日本への評価はけっこう厳しい。戦後民主主義や平和主義に寄り添う人たちが納得する。そしてそのあと「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と来ます。ここでまた保守的な人たちが喜ぶのです。
戦後50年の村⼭談話では、近代日本の植民地主義や軍国主義、さらに実際にアジア諸地域に与えた惨害への強い反省と謝罪が打ち出されました。戦後60年の⼩泉談話は、村山談話を踏襲しながらも、謝罪のカラーを少し薄めて、明るい未来志向に切り替えようとした。安倍談話はというと、小泉談話の線を大胆に先に進めました。日本に極めて問題はあったけれど、表立っての謝罪はそろそろおしまいにしたい。ここが明治への高評価と相まって、保守的・右翼的・愛国的心情の人々を満足させたと思います。
しかし安倍談話の未来志向の核心は、謝罪はもういいのではないかという文言の続きにあったのではないでしょうか。「それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります」。外への謝罪は一区切りにしたいとのニュアンスを滲ませながら「世代を超えて」歴史と向き合い続けろという。それはもう従来の反省と謝罪でしょう。私の解釈では、言外の意味こそ重要なのではないかと。安倍政権の唱えた「積極的平和主義」をご記憶でしょうか。日本一国として今後は悪に手を染めませんと謝る消極的平和主義から、国連や日米同盟や自衛隊を活用して世界の安心と安定に貢献する積極的平和主義へ。この転換を果たしてこそ敗戦国の卑屈さからついに脱却できる。これが安倍史観の真髄ではないですか。
石破氏の立場も安倍氏と根本では違わないと思います。でも安倍談話では反省が足りていないと思っていたのでしょう。対外的によりも対内的にです。安倍談話では満洲事変以来の国際秩序から逸脱する流れを国内政治のシステムが抑止できなかったと述べられていながら、そのシステムの具体的問題を指摘していない。70年、80年、謝罪したからもう良いということではない。システムの問題を自覚して直してきた歴史があれば大丈夫かもしれない。が、そうでなかったら、積極的に世界平和に貢献するつもりで、また昔と似た失敗をしかねない。その危機感が石破所感の出た理由ではないかと思います。
──確かに今回の所感では、これまでの談話ではあまり⾒られなかった「なぜ戦争を防ぐことができなかったのか」に焦点が当てられていました。そのなかで⽯破さんは5つの問題点の中の⼀つとして、明治憲法における統治機構に問題があったとしています。先⽣は具体的にどのような問題があったとお考えですか。
まず、現在の憲法、すなわち⽇本国憲法では議院内閣制が採られていて、政党が⽴法府である国会と⾏政府である内閣の両⽅を⽀配しています。そして⾃衛隊は内閣のもとに置かれていますよね。⼤⽇本帝国憲法下ではこれが⼤きく違って、いちばん上に天皇がいる。そのもとに国会と内閣が原則関係なく並立した。大正期の原敬⾸相の頃からは議会の多数政党が内閣を作り、政党内閣の時代と呼ばれますが、それは当時のデモクラシーの風潮でそうなったので、法制度の裏付けはありませんでした。首相は天皇が任命するもので、官僚でも軍人でも政党のリーダーでもよかった。
さらに、今では内閣のもとに置かれている軍隊(⾃衛隊)も、旧憲法下では独⽴していました。国会と内閣と軍部とが横並びで、束ねられるのは法的には天皇だけ。しかし、天皇は主体的に決断しないのが明治以来の憲法解釈の常道なのです。下々が良きにはからえということ。そうなると⼤きな決断が必要なときにしばしばうまくゆきません。
意思統一がしにくく、責任の所在も不明確になりがち。阿吽の呼吸で何とかしましょうみたいになる。なりゆき任せの政治になる。このような⽇本の旧憲法下での組織の縦割り制が仇となって、戦争を⾷い⽌められなかったと、⽯破所感は伝えたかったのかと思います。
──所感では、国会や内閣、軍部を媒介する存在として、元⽼などの「超憲法的存在」が挙げられています。戦前の⽇本において、これらの存在はどのような役割を果たしていたのでしょうか。
明治維新は王政復古で、天皇中心の国家体制を求めました。振り返れば、天皇は摂関政治や院政や幕府政治によって力を奪われてきた。そこで旧憲法は摂関や将軍の再来を防ぐため天皇の下の権力機構を神経質なまでに縦割りにしました。が、それでは国家が四分五裂してまとまらない。そこで活躍したのが元老です。伊藤博文や山縣有朋など。明治維新の功臣の中でも首相を経験した大物たちが元老に選ばれました。
でも元老には法的裏付けはありません。憲法にも出てきません。それなのに次の首相を決めたりして国を動かしていました。⽇露戦争のときに指導力を発揮していたのも、首相の桂太郎よりも元老の伊藤や山縣でした。旧憲法の縦割りの弊害を、超法規的な元老が乗り越えて、そのおかげで国が機能していた。しかし、元老は幕末維新に活躍した世代に限定されているので、時代が下ると消えていきます。そうすると当然ながら明治国家体制というのはうまく回らなくなるのですね。リーダーシップが取れない。決められない政治になる。たとえば軍部が勝手な行動をとっても誰も止められず追認してしまうとか。
昭和になって日中戦争が始まると、意思統一がとれないのは致命的です。戦争指導も和平への模索も、国家のコントロールが利かなくて、官僚も軍人も勝手をするので、まとまらない。これではまずいと近衛⽂麿首相が試みたのが大政翼賛会運動でした。貴族院と衆議院の国会議員を大政翼賛会という巨大政党に結集させて、その総裁が首相になって翼賛会内閣を作ると、官僚も軍も翼賛会の言うことをきくだろうから、決められる政治が実現すると考えた。しかし右翼に反対されました。⼤政翼賛会は天皇をないがしろにする現代の幕府だ。ナチスやソ連の共産党の真似だ。一党独裁だ。けしからん! 近衛はひるんで、大政翼賛会は名ばかりの実力なき組織になってしまいました。
──縦割り組織の解消は困難だったということですね。
そうです。混迷が続くうちに、太平洋戦争も強い決断のないまま成り行きで初めてしまい、敗戦に至りました。
──今回の所感全体を通して今⽇の私たちが持つべき教訓について教えてください。
今回のメッセージを通してこの昭和20年までの歴史を振り返ることで、今の⽇本の政治状況に対しても教訓を与えてくれると思います。縦割り組織であるとか、雰囲気や勢いに流された非合理的な政治とか、そういった戦前・戦中の⽇本の問題点が戦後に解決して今日に至っていると言えるのか。憲法が変わっても実は同様の問題が残り続けているのではないか。そんなメッセージも込められているのではないかと思います。
あと、今回の所感の中では政治や軍隊の問題だけでなく、マスメディアのことにも触れられていました。マスメディアが、健全な批判精神を失って、ポピュリズム的な⽅向に⾛って、国民を煽っていたのが戦争に向かう時代でした。これまた今⽇の⽇本に重なりませんか。最初に⾔った通り、石破所感には、安倍談話のような勇ましさや調子のよさはありません。でも真実の歴史とはそういうものなのです。噛めば噛むほど苦い教訓が溢れてくる。そういう所感でしょう。
(⾼橋央祐)