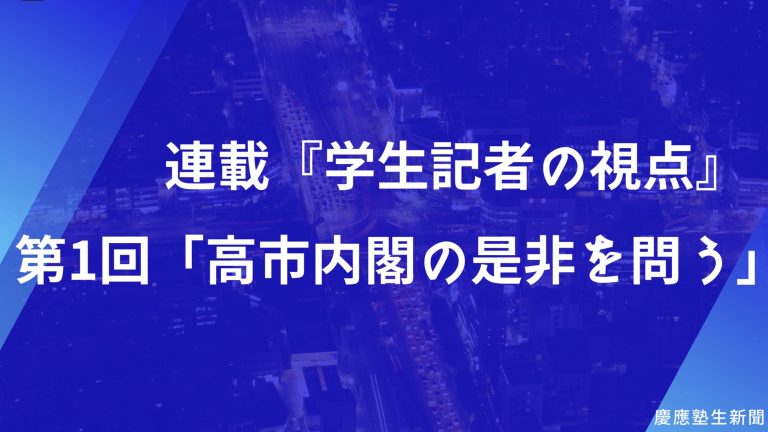前編はこちら
持たざる国
自らの国土を、世界の東端に位置づけていた古代日本の人々。しかし産業革命以後、西欧諸国の台頭により、独立を保つための国家作りが急務となった。
辺境の「持たざる国」としての「恐怖心」をバネに辛くも日清・日露戦争に勝利すると、列強の仲間入りを果たし、ようやく自由で平和的な気風の大正時代が訪れる。だが、その頃、遠くヨーロッパの地では、悲劇的な戦争が勃発していた。
慶大法学部の片山杜秀教授は、この第一次世界大戦からの一連のできごとが、日本の運命を大きく動かしたと分析する。
国民の選択
第一次世界大戦は、日本社会にも大きな影響を与えた。軍需により日本経済が一気に潤ったのである。国民は、さらなる経済成長を望んだ。
「国民が願ったのは経済的な利益でした。その為にはもちろん貿易という選択肢もあるわけだけれども、ヨーロッパ型の膨張主義、植民地主義も捨てがたい。国民が重要視したのは平和ではなく、自分の国と自分たちがひたすら豊かになるということだけでした」
より豊かになるために-。大正時代には自由貿易、国際協調的な路線が試みられた。
だが1929年、世界大恐慌が発生する。世界の列強国家が軒並み経済的な打撃を受けるなか、国際社会と命運を共にしていた日本経済も例外ではなかった。
「国際協調路線をとると、世界経済の影響をもろに受けてしまうことがわかりました。むしろ、ブロック経済やソ連の計画経済の方が優れているように見えた。そこで、ソ連を見習って、本土と植民地で計画的な経済をまわせば、世界経済の一挙一動を気にせずに済むという考えが生まれました。国際協調の可能性を探るのではなく、どうやったら自分の国を守れるか。どうやったら多くの利益を得られるのかという視点しかなかったのです」

「尊皇攘夷」の帰結点
世界恐慌以後、このような考えの持ち主が増加の一途を辿った。満州や朝鮮をはじめとするアジア諸国を支配してアジアの盟主になろうという思想が、大多数の国民の支持を得た。片山教授はそこに、江戸からつづく「尊皇攘夷」思想の完成形をみる。
「『小国である日本が、外国と戦争をしても負けるだろう。だから日本が強国になった際に再び攘夷を実現する』という江戸時代以来の思想が形になった瞬間です。実際、この時期には尊皇攘夷を訴えた『水戸学』の書籍が再評価され、大変ブームになりました。『恐慌でヨーロッパが没落する一方で、今後日本はファシズム的な統治によってアジアの支配を実現できる。そうすれば、大東亜共栄圏が簡単に完成する』という考え方が訴えられたのです」

未完のファシズム
1932年5月15日-。犬養毅首相が急進派の海軍青年将校に殺害される。軍部の発言力が高まり、事実上、政党政治は崩壊することとなる。
「政治政党の人気は急速に失われていきました。国民の支持は軍隊に移り、従来の政党政治は終わりを告げました。国民が政治権力に抑圧されたのではありません。国民自身が政党ではなく軍人を選択したのです。この点を認識し、反省しなければ当時の歴史は語れません」。
代わりに生まれたのが挙国一致内閣だ。その実情は軍部独裁というよりもむしろ、長期的な展望に欠けた、まとまりのない政治集団だったという。
「短期的、近視眼的な決定が繰り返され、結果として日米開戦に繋がってしまったのです」
片山教授は、この政治体制を「未完のファシズム」であると捉えている。天皇を中心としたシステムを構築してしまったが故に、実質的に各政治勢力の統率をとる人物が存在しなかったのだ。故に、なかには非常に過激な思想の持ち主もおり、日本政治に大きな影響を及ぼした。その代表例が満州事変を引き起こした陸軍士官、石原莞爾である。
「石原莞爾は、法華経のユートピアである日本が、東洋VS西洋の世界最終戦争を勝ち抜き、世界を統一するというカルト宗教じみた考えを持っていました。ある意味、「尊皇攘夷」思想の続きでしょう。当時から過激な思想だとみなされていましたが、それが後追い承認されていったのです」
無論、政府や国民が彼の行動を容認したのは、それが当時の日本社会の利益や思想と合致する部分があったからだと片山教授はいう。
「当時の中国は権力が分散しており、情勢は不安定でした。『日本が傀儡政権によって中国を支配することにより、新たな秩序が構築されるだろう。それを国際社会も認めるだろう』と日本の人々は錯覚していたのです。ですが、その実情はただの侵略行為でした」
情報が錯綜し、万人が自分たちの信じたいものを信じていた。過激思想の持ち主を抑止する力も無く、政治システムも機能しているとは言えない。それこそが「未完のファシズム」の実態だったのである。
日本製ファシズムの可能性
一方で、もしも日本におけるファシズムが、狂信的な指導者の下、「完成」していたとしたら-。更なる悲劇が起こされていた可能性も捨てきれないと片山教授は考える。
「仮に石原莞爾が権力を掌握し、彼の思惑通りに事が進んでいたとしたら、恐らく日本は崩壊していたでしょう。彼の計画では、太平洋戦争を起こさずに東亜連盟独裁政府を作り、国力がつき、核兵器を開発した上で、60年代に最終戦争を仕掛けることになっています」。
しかし、幸い史実では、彼が政権を奪取することはなかった。
「石原莞爾の計画は現実味がない絵空事と言わざるを得ません。いざ満州国を建国したものの、彼本人は気力の続かない人でしたから、具合が悪いと言って途中で全て投げ出したわけです。全くもって最悪です。おまけに戦後は『俺をA級戦犯にしろ』と息巻きながら、病死してしまいました」。
当時の日本社会は、徹頭徹尾「未完のファシズム」でしかなかったのだ。

終戦
そんな「未完」の国家であった大日本帝国は、太平洋戦争で崩壊を余儀なくされる。絶対国防圏は1944年の早い段階で崩壊し、敗色は濃厚だった。にもかかわらず軍部と政府は戦争を継続する。本土空襲により多くの命が失われ、広島と長崎には原子爆弾が投下された。
そこでよく問題となるのは、なぜ日本は早期に降伏しなかったのかという点だ。
「彼らはある意味、国民を骨の髄まで洗脳し、戦争に動員していました。戦争を継続しなければ、相当な反発が予想されたのです。各地で反乱が起きたでしょうし、最悪クーデターも発生していたでしょう。45年夏の段階まで降伏が出来ない程、当時の日本は袋小路に入り込んでいたのです」
現代
1945年8月-。日本は遂に連合国軍のポツダム宣言を受け入れ、日本における戦争の時代は終わりを告げた。あの夏から76年、日本に生きる私たちは平和な時代を享受している。
しかし、近年、現代の社会の様子が徐々に戦前のそれに似通ったものに近づいていると、戦争を経験した人々は警鐘をならす。実際に当時と現在の状況は似ていると言えるのか。
「現代と当時の最大の相違点は、戦争への参加や植民地主義が国の経済発展とは必ずしも結びつかないことです。当時の日本は、右肩上がりの経済成長の時代、その延長線上に戦争へと突入していきました。一方、現代の日本は、経済的な低迷が続いています。むしろ平和を重視する戦後民主主義の時代に経済成長を経験しました。戦争の反省を上手く活かした時代です」
戦前の昭和と現在では、日本を取り巻く社会状況がかなり異なっているということだ。だが、片山教授は日本を対外戦争へと突き動かしていたもうひとつの要因が、現代にも存在していると感じている。
「日清・日露戦争期に日本が抱いていた、「持たざる国」としての『恐怖心』です。『このまま国が没落してしまうのではないか。近隣の大国に制圧されてしまうのではないか』と多くの人々が恐れているのではないでしょうか。今日も国家を守る為の軍事力が大いに議論されています。また、医療や社会福祉の環境が保てるのかという不安も国民の間で高まっています。そんな中、ばらばらになりかけている人々を何とか繋ぎ止めるために、為政者は『恐怖』を煽って『国家の威信』を保つことに躍起になっているわけです。これはある種『尊皇攘夷』の考え方にも似ています。戦前と同じく不安定な国際情勢の中で、今度は選択を誤ってはなりません」

今こそ独立自尊を
戦争の反省を活かし、正しい選択をする為に-。片山教授はそのヒントを慶應義塾の設立者、福澤諭吉の思想に求める。
「中産階級の復活が必要です。世界恐慌の際に戦争が起きたように、国内の経済や社会に不安があると、どうしても人々は外側に『突破口』を求めてしまいます。個々人が豊かに、ある程度満足した暮らしをしていれば、人々が進んで好戦的になることはありません。もしも貧富の格差が生じ、真の『豊かさ』が壊れているのならばそれを埋める必要があります。まさに『一身独立して一国独立す』です。まずは、日々の生活を大切にして一身を独立させる。その上で貧苦に苦しむ人々も救う。その気持ちを皆が共有すれば間違った方向に進むことはないと考えています」
第2回につづく
(石野光俊)