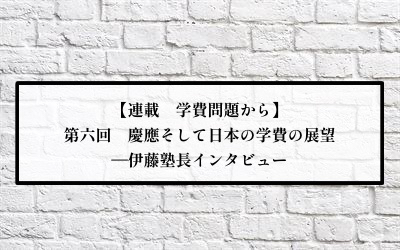病気、そして病気が引き起こす死への恐怖は人から笑顔を奪う。対して、病気を抱えて死を意識することの多い病院で患者たちを絶望から救い出し、笑顔にする仕事をしている人がいる。慶應義塾大学病院緩和ケアセンターでは、病気の全段階で生じるさまざまな痛みを和らげ、より良い生活を送るための支援が行われている。そこに携わる、精神科医の白波瀬丈一郎氏に話を聞いた。
「痛み」には、身体的な痛みと精神的な痛み、社会的役割など人間の尊厳を維持できないことで生じる痛みがある。緩和ケアセンターでは麻酔科・精神科の医師や看護師、薬剤師、臨床心理士などが協力して、患者それぞれの痛みを軽減するための支援をしている。
中でも、精神科医は患者と話をして、どのような痛みなのかを見極めるということを行っている。同じ「心が沈んでいる」という症状でも、身体的痛みが強いことが原因の場合や、仕事に行けないことによる経済的な問題が原因の場合などがあり、支援の仕方も異なってくる。だからこそ、しっかりと話を聞くことが大事なのだ。
患者に対し具体的なアドバイスも行う。ディグニティー・セラピーという手法では患者の人生を歴史のように書き出し、手紙にして、自分の歴史を受け継いでくれる人や知ってほしい人に渡す。こうして、次の世代に何かを残すことで患者の尊厳を守るのだ。
また、「外傷後成長」という考えを用いることもある。これは、人は辛い経験からも学び、人間として成長できるという考えだ。病気になるということは絶望的な経験だが、人はその経験をもとに、新たな価値観や生きる意味を見出していける。絶望を乗り越え成長しようとする患者の心の動きを捉え、支えていくという。
かつて、緩和ケアは積極的治療が望めなくなった患者を対象とするホスピスや終末期医療と同じに捉えられていた。しかし現在は、たとえ治療が十分望める段階であっても患者がストレスを受け、苦しんでいれば、積極的に提供されている。また、緩和ケアは患者本人だけでなく、患者の家族や治療に携わる医療スタッフも対象に行われている。無力感に苛まれたり、自分を責めたりする家族や医療スタッフにも支えが必要だからだ。
白波瀬氏はこんなことも語った。「患者さんから痛みを取り除いて穏やかに最期を迎えられるように支援することが緩和ケアの重要な役割です。ただ、それだけではなく、患者さんの死を看取り、その後も生きていく人のためにも必要だと思います」。家族や医療スタッフがやがて来る患者との別れを受け止め、支え合い協力して見送ることができたと感じられれば、これからの人生を前向きに生きていこうと思えるという。
「笑顔とは希望を持つこと」。緩和ケアで行っているのは、多少無理してでも希望を見つけ、絶望させないことだという。絶望的な状況においても、現実を見つめ、忘れがちな希望を見つける。そうして辛いことや悲しいことに向き合い乗り越えた先に、笑顔はあるのだ。
(井上知秋)
【特集】笑顔のつくり手たち