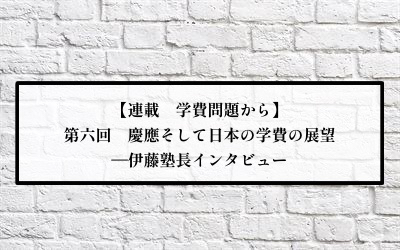慶應義塾大学医学部解剖学教室およびノエビア神経変性疾患寄附講座の研究グループは、アミノ酸の一種である「D—セリン」が筋萎縮性側索硬化症の進行に関わることを発見した。この発見により、今後ALSに関して新たな診断・治療法が期待される。
筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis以下、ALS)とは、運動神経が徐々に冒されることで全身の筋肉の萎縮と筋力低下を招く神経変性疾患である。病気の正確な原因は未だ解明できておらず、難病に指定されている。
慶應義塾大学医学部解剖学教室(相磯貞和教授、笹部潤平研究員)およびノエビア神経変性疾患寄附講座グループは、「D—セリン」がALSの進行に伴い過剰産出されていることを、ALSモデル動物とALS患者由来の脊髄において確認した。「D—セリン」はグルタミン酸による興奮作用を促進することで知られ、神経細胞周辺のグリア細胞から放出される。
今回の発見はグルタミン酸による神経の過剰興奮がALSにおける運動神経死の原因であるとする仮説とグリア細胞から毒性因子が放出されるという2つの仮説を密接に結び付けた発見である。
グリア細胞はもともと神経細胞に栄養を与え、その働きを補助する役割を持つ。しかし、グリア細胞が活性化することでそこで産出される「D—セリン」が増え、それによりグルタミン酸毒性が増強され運動神経にダメージを与える。そのダメージによりさらにグリア細胞を活性化させ、また「D—セリン」を産出するという悪循環が発生する。
この「D—セリン」の働きを阻害することでグルタミン酸の毒性も弱められ、結果として運動神経細胞死が抑制される。そのため、現在治療薬として唯一認可されているグルタミン酸阻害薬に加え、この「D—セリン」に働きかけることにより、より良い治療法の開発の可能性がある。また、「D—セリン」はALSの進行に伴い増加するため、今後は病気の進行を数字として評価する指標としての利用が期待できる。
なお、この研究成果は「The EMBO journal」(volume26,Number18September19,2007)に掲載された。